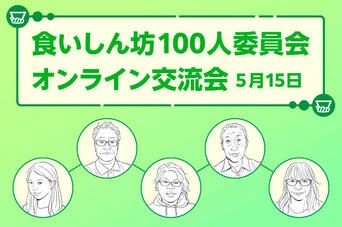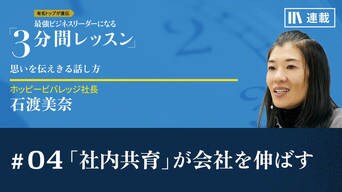ただひとつ違う点は、中国の方からは、産科事情の遅れについての嘆きを聞くことが度々あるということです。上海在住の陳東華さん(40歳、仮名)は、「中国の産婦人科では、ひとりの人として、女性として扱われない」というのです。陳さんが、昨年、月経痛で診察を受けたところ、子宮筋腫が見つかりました。心配になり、「妊娠に影響しませんか?」と男性医師に尋ねたところ「その年では子宮は要らない、取ったほうがいいよ」と、冷たく言われたそうです。
中国ではこのように男性医師が、女性を傷つけるような失礼な言葉を投げかけることが、よくあるようです。日本でもかつては、高圧的な医師が女性を傷つけることがありました。そうした被害を受け、精神的に傷ついた女性を受け入れるのも、私たちの役目でした。まだ日本にもひどい医師はいるかもしれませんが、いまレディースクリニックが日本各地に広がっているのは、かつてそうした状況があったからです。つまり中国はまだその歴史を経ていないということでしょう。
もちろん、中国にも、女性の悩みに誠実に向き合う医師はいるでしょう。ただ、その数はじゅうぶんではないようです。医療の質も、全体のレベルとしてはまだ発展途上と言えるのかもしれません。
日本のレディースクリニックのなかには、そのような状況を見て、中国に進出しているところも出てきています。そうした動きは今後も増えていくかもしれません。
しかし、誤解されたくはないのですが、私はただ「日本の産婦人科はすごい」と言いたいわけではないのです。すでに医療の質という観点から見れば、日本は「技術」の高さにおいて最先端ではありません。特に、私たちが関わる高度生殖医療と言われる領域で、それは顕著に表れています。
日本の医療技術は後れをとっていく
研究の規模の問題・資本力の問題や、日本の医師や研究者が、技術の研鑽や勉強に費やせる環境が世界に比べて劣っていることなど、さまざまな背景があります。
さらに「倫理的な問題についての議論が不十分だ」という理由で研究が進まないという事例もあります。「どこまで遺伝子解析・操作が許されるのか」「新たな技術は自然な人の生殖といえるのか」。もちろん、そうした議論は必要です。しかし、日本で「議論を重ねている」と言っても、この数年間でどれだけ進展があったでしょうか。その間にも、世界では研究がどんどん進んでいるのです。